8月8日に、「令和5年度やまがた学校改革推進協議会」の第1回を対面とオンラインのハイフレックスで開催しました。この協議会は、文部科学省「教員研修の高度化に資するモデル開発事業」の一環として実施したものです。当日の参加者は、本事業に関わる山形県内の学校および山形県教育委員会、山形県教育センターの関係者など、42名(対面参加30名、オンライン参加12名)でした。山形新聞と本学のプレス・リリースで本事業について知った宮城県の現職教職大学院生の参加もありました。
現在、日本の教職員は、忙しく勤務しているにもかかわらず、十分な研修時間が確保されていません。「学びたいけど学べない。」という状況が、多忙感をいっそう強めています。このため、現場で学ぶ教師をエンパワーする学校内外の教員研修の充実が、喫緊の課題になっています。こうした課題の克服を目指し、教育実践研究科と地域教育文化学部では、山形県教育センター、山形県教育委員会と共に、全国に先駆けた新たな教員研修のモデル開発に着手しました。今回の協議会は、そのスタートとして企画されたものです。
当日は、出口毅副学長の挨拶のあと、前半は、中西正樹研究科長が座長をつとめ、次の報告がありました。
(1)本事業の全体像とねらい
(2)山形県教育センターの「学校マネジメント講座」の進捗状況
(3)本事業で整備する学校内研修スペース「学びカフェ」について
報告の中心は、本プロジェクトにおいて共有すべき哲学(「Open, Transparent, Flexible, Accountable」)の提示と、その具体例としての公立はこだて未来大学、河北町立谷地南部小学校の取組みの紹介でした。(「哲学」とは、「基底になる考え方」を意味します)。忙しさの中で、教職員一人ひとりの個性的な「人となり」や実践は共有されず、見えなくなりがちです。本プロジェクトの「学びカフェ」は、それを打開することを目指し、各校の状況に即した柔軟な運営を目指します。
協議では、「世界と比較して、日本の教員の自己研修にかける時間の減少が印象的」という指摘や、「日本の教員は、パブリックな面とプライベートな面が重なる多面的な存在である」という指摘がありました。
 |
 |
| 前半の報告の様子 | 後半の対談による問題提起 |
後半は、「新人教師の悩みとこれからの研修に期待すること」として、ディスカッションを行いました。佐藤瑞紀さん(新庄市立新庄小学校教諭、教職6年目)と森田智幸准教授による対談の問題提起のあと、江間史明教授のコーディネートにより参加者同士で話し合いをしました。話し合いでは、「どこの学校でも多忙感があり、若手の先生方が悩んでいる現実があるのだと実感した」という指摘がありました。
 |
 |
| グループで協議する参加者① | グループで協議する参加者② |
協議会後の感想では、参加者から、次の声がありました。「学びカフェの構想が今後、山形県で広がり、どこの地域でも、学校が大学や県教育センターと連携しながら児童・生徒の学びをサポートできるよう、レベルアップできるようになることを期待したいです。」「皆様の熱い思いが伝わってくるとともに、新しいプロジェクトへの期待感がこみ上げてきました。」
今年度の本協議会は、第2回を12月17日(日)、第3回を来年の2月15日(木)に予定しています。ご関心をお持ちの皆さんの参加をお待ちしています。
■対象学部・研究科等
人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部、養護教諭特別別科、社会文化創造研究科、
理工学研究科(理学系)、教育実践研究科
■日 時 令和5年3月24日(金)午前10時開始
*開始15分前までに入場してください。(厳守)
■会 場 山形県体育館(山形市霞城町1-2)
*父母等の式典へのご臨席については、感染対策を徹底した上で可能とします。
マスク着用、当日朝の検温等、下記留意事項にご協力願います。
*新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、在校生の見送りについてはご遠慮願います。
◆留意事項
1 出席前は体調管理を徹底してください。
2 当日は、会場に来る前に必ず検温し、発熱や体調不良の場合は、出席を見合わせてください。
3 県体育館のある霞城公園内の駐車場は、式典来場者及び送迎等では使用できません。
来場時は公共交通機関を利用するなど、式典の円滑な運営にご協力願います。
近隣商業施設の駐車場利用及び路上駐車は、多大なご迷惑をお掛けすることになりますので、ご留意ください。
4 式典前後は、記念撮影などで会場周辺に留まることなく、速やかに移動、解散してください。
5 会場でのマスク着用にご協力願います。
なお、卒業生・修了生においては、個人の判断により式典中はマスクを外しても差し支えありません。
6 座席番号を記録してください。※記録方法については、当日会場で指示をします。
7 在学生の見送りは禁止します。
令和4年度の「第5回学びのフォーラム」は、8月に2回、12月に1回の合計3回の開催となりました(主催: 大学院教育実践研究科・地域教育文化学部、後援:山形県教育委員会)。
今回のフォーラムでは、これまでに引き続き、「学ぶとはどういうことか」を主題に、高校生・大学生・社会人 の合同でゼミナールを行いました。平成27年度から、高校生と大学生を対象とした合同ゼミナールを始めて、 今回で 8回目になります。今年度は、3回の開催で合計125名(高校生37人、大学生27人、社会人61人)の 方に参加していただきました。参加した高校は、次の 14 校でした。新庄北高校、北村山高校、東桜学館高校、 谷地高校、寒河江高校、山形北高校、山形西高校、山形南高校、長井高校、酒田東高校、酒田西高校、鶴岡南高 校、鶴岡北高校、鶴岡東高校。
今年度は、8月に初めて置賜地区(山形大学米沢キャンパス)、庄内地区(山形大学鶴岡キャンパス)において開催しました。「学びのフォーラム in 置賜」の当日8月 4日(木)は、豪雨とそれに伴う河川の増水等の影響により、公共交通機関の運休や主要道路の通行止めなど、実施の可否を直前まで検討せざるをえない状況でした。 そのため、当日朝にオンラインに限っての実施を決定しました。難しい状況にもかかわらず、4人の高校生、3人の大学生、3人の社会人の合計10人の参加がありました。参加した高校は、長井高校、酒田西高校の 2 校でした。
8月10日(水)の「学びのフォーラム in 庄内」は、7人の高校生、6人の大学生、11人の社会人の合計24人の参加がありました。参加した高校は、酒田東高校、酒田西高校、鶴岡南高校、鶴岡北高校、鶴岡東高校、新庄北高校の6校でした。数多くの高校から参加していただいたことに深く感謝いたします。
3回目(小白川キャンパス開催)の「第5回まなびのフォーラム in 小白川」は、12月18日(日)に開催しました。この日は、テキストの著者である佐伯胖氏(東京大名誉教授)をお呼びして、テキスト第3章「『遊ぶ』ということの意味」の節を読み、「学び」と「遊び」の関係について考えました。その中でも、特に、「ゲーム」の世界やスポーツにのめりこむことの意味をどのように考えればいいのか考えました。「ゲーム」や「スポーツ」は、見方によっては「賞金」や「商品」の獲得を目指した活動のようにも見えます。一方、見方によっては、「遊び」と「学び」とが混然一体となった活動にも見えます。高校生、大学生、社会人とがグループで考える中で生じた、この疑問に対する答えを考えることにしました。
佐伯氏からは、「スポーツ」にのめり込むことの意味を、「想定外」と対峙することのおもしろさとして考える重要性について話題提供がありました。サッカーワールドカップの試合や、大谷翔平選手に魅せられる点はどこにあるのでしょうか。佐伯氏によれば、それは、選手がいつも「想定外」と対峙しているからです。「想定外」と 向き合う、その緊張感にこそ、おもしろさがあります。授業に「想定外」との対峙は、どれほどあるでしょうか。「賞金」や「賞品」の獲得は、「想定外」の事態への向き合い方に対する評価です。それは、事前に基準があってなされている評価ではなく、「後付け評価」です。「想定外」と向き合い、その結果生まれた様々なものを「味わうappreciate」することが「評価」です。日常的な教育活動における評価は、こうした「後付け評価」となっているでしょうか。昨年度同様、J.デューイが、著書 How We Think の中で、遊び心 playful と真剣さseriousnessとは、同時に成立しうると述べていることも合わせて紹介されました。日常の教育活動に、その両立は実現されているか、参加者各自が改めて見つめ直す機会となりました。来年度も、参加者が直面している「学び」の場を再考する場として、本フォーラムを開催します。皆様のご参加をお待ちしています。
以下に、参加者の方からいただいた感想を一部紹介します。
【高校生】
・とても楽しい時間でした。学年、年齢が異なる方々とグループになって、違う目線で意見を交わし、確かに!って思ったり、知らなかった!と思ったり、いつもクラスの中で同じ学年の人と話してるのとはいい意味で全く違う感覚でとても新鮮でした。
・今まで"考える"を考えたことがありませんでしたが、学びのフォーラムのお陰で考える機会になりました。ありがとうございました!普段何気なく行なっていることだからこそ、日常を振り返り見直すことができました。学びのフォーラムの1番の魅力は、高校生、大学生、そして先生が一緒に意見交換をすることだと思います。違う日常で違うことを考えているので様々な角度から物事を捉えることが可能になり、より理解を深められました。
・今まで勉強するときに、コスパよくやろうとしたり、点数だけ取りに行こうとしたりして定着に至らないことが多々ありました。遊び心をプラスすることで、いつもつらい気持ちで取り組んでいた勉強が楽しみになる気 がしました。今日の話を忘れず学び続けていけたらいいなと思います。
・人と意見を交換し合うことはすごく楽しくて、現役の先生の意見も聞けたので参加してよかったと感じた。先生からの視点でどのように生徒を思っているかは普段聞けないので貴重な体験ができた。高校生は他人の評価を恐れていることが多く、遊び心がなくなってしまうことも多い。今日の話を聞いて、遊びがなければ学びもないことが分かり、これからの生活にも、人生でも、遊ぶことを意識するべきだと思った。自分は教職、山大を目指しているのでまた来たいです。
【大学生】
・初めて参加させていただきました。現役の先生方と高校生のみなさんとの交流を通して、時には高校時代を強く思い出し、時には自分の将来像をイメージするなど、普段の大学(講義)では得られない考え方や知識を身につけることができました。今の学校教育の中で「勉強」と「遊び」を結びつけることは難しいのではないかと感じていましたが、今回のフォーラムを通じて、少しヒントをもらえた気がしています。これからの大学生活、そして、自分が描く教師像に大きく生かしたいと思いました。ありがとうございました。
・大学のゼミでは、「いいこと思いついちゃった」、「ねぇ、きいて」と伝えて一緒に考えることで学びを実感できるのに、教育実習では、「進めよう」とか「評価」とか考えてしまうなぁと思いました。
【一般】
・初の庄内会場でのフォーラムに参加できたことを光栄に思います。年齢や職業など様々な属性の違いを越えて学び合うことの良さを実感しました。学校の教室の学び以上に、複雑なインタラクションとわかり合いが起きることに気付くことができて、大変有意義でした。
・様々なお立場、経験、年齢の方と同じテーマでお話しする時間は大変有意義だった。自分の見方が広がることで、新しい気づきや自分の考え方を練り直すきっかけになります。がっちり教え込まれて、前を向いてしっかり聞き、しっかり書く(黒板を写す)、今日は○○がわかりましたね!という方法で育ってきた自分にとっては、慣れるまで対話を続けていく学び方には違和感がありました。後からじわじわと効いてくる、そこで完結しないからこその学びは楽しいし、ワクワクしてきます。子どもの前に立つ教師として、こんな学ぶことの楽しさやワクワクを子どもたちに与えていきたいです。この 1 年半、眠っていた感覚が戻った時間で、本当にいい刺激になりました。楽しい時間でした。
・教員OBの立場として、「教育を語る」喜びは幾つになっても変わらないものである。しかし高校生とは 50 歳以上の年齢差があるが、彼女らの純粋な言動と感性から大きな励ましをもらった。切実なのは、若き優秀な者たちが教職を目指さないこと。このフォーラムにもう少し多くの高校生の参加を促して、教育の魅力と面白さと不可思議さを先輩が熱く語り継ぐ必要がある。それは地元に根差した地方大学の責務でもあるだろうし、私達教員OBの役割でもある。
・学部生のころに参加した「学びのフォーラム」と、教員になってからの「学びのフォーラム」は、文献の見方も、同じグループの方や佐伯先生の話の解釈も変わりました。4 月から担任として子どもたちと過ごす日々は とても楽しいですが、本当にいろいろなことが起こり、まじめな心だけではやっていけないこともたくさんあり ます。佐伯先生のお話にあった「想定外のことに体をひらくこと」「いいこと思いついた」は、明日からの子どもたちとの生活で大事にしていきたいと思いました。
・高校生のころから参加して、何度も「勉強」=「学び」―「遊び」だということについて考えてきたつもり だが、いざ教員として働いてみると「遊び」、できていないなと感じました。「それおもしろいね」と子供に巻き込まれてみるというのも大切だと思いました。
・「遊び」とは?「学び」とは?「能力」とは?という話題にはこれまで結構なってきたが、今回の「評価」が話題になったのは個人的にすごく楽しかった。働いているとますます「できる」とか「わかる」とか「学ぶ」と いうことが何だろうと考え始め、自分自身が「能力信仰」「勉強」に浸食されていることに気づく。ポジティブじゃないとやっていられない!!子どもの前に立っていられない!という日々の中でも、「いいこと思いついた!」 を即試せるのが教師の魅力だということに今日、気づかされた。
1月20日(金)に、山形大学地域教育文化学部・山形県教育委員会連絡協議会を開催しました。
本協議会は、山形県下の教育の発展と教育水準の向上を図るため平成17年に設置され毎年意見交換を行っております。
近年は、コロナ禍により開催が見送られておりましたが、当日は、県教育委員会からは髙橋教育長をはじめ12名の方から出席いただき、また、山形大学からは地域教育文化学部長、附属学校園の各校長・園長はじめ19名が出席し、数年振りに対面による協議会を開催いたしました。
今年度の協議会では、山形県の抱える教育現場の課題、大学の教員養成の取り組み、県教育委員会と山形大学が連携して行う研修のあり方、附属学校の新たな取り組み等を中心に種々意見交換と活発な議論が行われました。
県教育委員会からは、教員研修や新学習指導要領に対応する県の取り組みの紹介等の説明、地域教育文化学部からは、教員を目指す学部学生や教職大学院の院生の修学状況の説明、取り組み等の実例を交えての紹介もあり、1時間半に渡る会議は、お互いの理解を深めるとともに山形の地域課題を再認識した貴重な場となり、今後も継続的に議論していくことを確認し閉会しました。
(会議の様子)
2022(令和4)年12月18日(日)に山形大学小白川キャンパスを会場にして、第10回やまがた教員養成シンポジウムを開催しました。
このシンポジウムは、大学院教育実践研究科と地域教育文化学部、東北文教大学、公益財団法人やまがた教育振興財団が主催し、山形県教育委員会の後援をえて、開催したものです。
当日は、61名の参加(対面23名、オンライン38名)がありました。 本シンポジウムのテーマは、「世代交代がすすむ山形県、これからの教員の研修と養成をどうすすめるか」でした。
現在、山形県では、新規採用者については、教員志願倍率が低下する一方、大量採用されている20代後半から30代前半の教員層の力をどうつけるかが課題となっています。また、40代からの教員層がうすく、今後の学校経営を担う人材の養成についても大きな課題となっています。こうした問題状況は、山形県だけではなく、全国的に共通するものと考えられます。そこで、本シンポジウムでは、これからの教員の研修と養成の在り方について、大学、学校、行政、そのほかの皆さんと広く意見を交換したいと考えました。
最初にお二人の先生からご講演をいただきました。
はじめに、福井大学の理事・副学長の松木健一氏です。氏は、臨時委員として参加されている中央教育審議会での議論を紹介しながら、教員養成から教師教育へという展望とそれを担う大学教員のコミュニティについて話をされました(オンライン参加)。
次に、福井大学連合教職大学院の森田史生氏です。氏は、これまで、教員として、あるいは福井県教育総合研究所の研修課長として教職大学院に関わり、現在は、教職大学院の実務家教員としてお勤めです。福井県における学校と行政、大学の連携の実際とそこでの学校や教職員の変容について話をされました。 質疑応答と討論では、活発な質問と講演されたお二人の応答がありました。
・学校改善における校長のリーダーシップと同僚性の構築については、中央教育審議会で管理職の資質・能力が議論になっている点や福井県における校長のスクールプラン(学校経営方針)を教職員が協働で読み解く取り組みが紹介されました。
・学部段階から、教職大学院の「理論と実践の往還」を位置づける今後の体制整備については、学部4年間を、教員になるための準備教育ではなく、生涯にわたる教師としての職能成長の一部として位置づける点が示されました。(その意味で、「理論」は実践者の外側にあるのではなく、実践者の内側にあって素朴なものから精緻なものへ洗練されていくものだと強調されました)。
このほか、教員の世代間を越えたクロス・セッションや学校改善におけるカンファレンスの方法への質疑応答もありました。
シンポジウムの事後アンケートでは、次のような声がよせられています。
・行政の研修も校内研修もパッチワーク型というお話には、反省しつつ納得しました。校内研修を、1年間あるいは数年を見越してデザインしていくこと、教員個々と面談しながらいかにその個性が生かされるよう助言していくか、校長としての役割は重いですね。
・何より、現在の研修スタイルは何十年も経過している。校内授業研においても、さらに指導主事の指導も何十年も同じことをやっている。違う目線で教育事務所の学校や教員への指導を考えていきたいと考えているのだが。
・研修には研修を主体的に受けとめる教員の姿勢はもちろんですが、それを支える学校組織のあり方や、研修の普及をどのようにすすめていくかが大切だと考えます。大学院での学びをどのように職場に活かすのか、個人のもので終わらせないためにはどのようにすればよいのか、ヒントをいただけたように思います。
・場違いなところにきてしまったかと思いました。しかし、これからの教員研修は、大学、附属学校、県教委等が垣根を越えて連携していくことが大切になることを実感し、大変勉強になりました。時間も資源も人材も限られているので、各組織の強みを出すことができる連携を考えていきたいと思いました。
コメントには、参加者それぞれの立ち位置から、これからの教員の研修と成長について考えを巡らせている様子が述べられていました。本シンポジウムは、今後の山形県における教員の研修と養成を考えて行く第一歩になったと考えています。 (江間史明・宮舘新吾)
 |
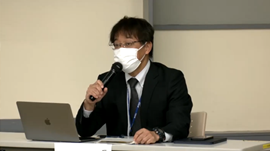 |
 |
 |

















